半年で15キロ痩せた
ダイエットマスターが贈る
365日で痩せる方法!
この記事の趣旨
第52話 「 腸活ー脂質改善編 第四話 」
肉や卵などの
脂質たっぷりの動物性たんぱく質食べすぎると
腸内環境が悪化してコレステロール値が上がりやすくなる。
ということを前回、学びました。
今回はさらに
肉に含まれる脂質に注目して
肉を食べる際の注意点や
一日にどれくらいの肉を食べて良いのか?
といったところまで、踏み込んでみたいと思いますよ!
お楽しみに♪
このブログの趣旨
このブログでは
毎日1記事読んで
実践すれば、誰でも
365日ですっきり痩せられる!!
をテーマに
20年後、お年頃になって
ダイエットを志した娘( 今4歳 )に
私が正しいダイエットを教える!
といった構成で
意志薄弱な、私が
半年で15キロ痩せられた
ダイエット方法を公開しています。

前回、前々回で
「 中性脂肪 」と「 コレステロール 」
について話したけど・・・
脂質に付いてのイメージは変わったかい?
ええ。
脂質も食べなきゃダメってことは
理解出来たわ。
でも食べちゃ駄目な脂質があるって
話だったけど・・・


そう。
今回から本格的に
「 脂質 」について学んでいくよ!
ハードな取組みも随時追加していくけど
ちゃんとついて来てね??
余裕よ。
睡眠改善を達成した私を
みくびらないでね。


頼もしい!!
「 肉 」に含まれる脂「 飽和脂肪酸 」についてまず知ろう

「 肉 」の話に入る前に、肉に含まれる脂について、簡単に学んでおきましょう。
まず 「 飽和脂肪酸 」 と 「 不飽和脂肪酸 」 の違いを知っておこう
油脂は、脂質の主成分「 脂肪酸 」の種類によって大きく二つのグループ。
「 飽和脂肪酸 」 と 「 不飽和脂肪酸 」 に分けられます。
これから、この二つの違いを説明しますが・・・
なんだか、ややこしくてつまらなさそうな話だな。と思った方。
ご安心ください。
ここで、理解して欲しいのは、たった二つだけです。
飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の違い
飽和脂肪酸:動物性の油脂に多く含まれる
常温で固体の脂
不飽和脂肪酸:魚や植物性の油脂に多く含まれる
常温で液体の油
飽和脂肪酸は、主に牛肉、羊肉、豚肉、鶏肉、牛乳、チーズなど、動物性の脂質に多く含まれまれていて、常温で固体。
不飽和脂肪酸は、主に魚やナッツに含まれる " 油脂 "や、 植物の種子からとれる油に多く含まれていて、常温で液体。
これだけ理解していただければ大丈夫です。
今回は動物性の脂質に多く含まれている「 飽和脂肪酸 」にスポットを当てて見ていきたいと思います。
「 肉 」に多く含まれる「 飽和脂肪酸 」は食べ過ぎに注意が必要!
鍋をした翌日。
鍋に残った汁の表面に、びっしりと浮いた真っ白い脂の塊を見たことがあるはずです。
汁が温かかった時には、溶けていた肉の脂が、冷めたことで個体になり表面に浮いた脂・・・
あれがずばり「 飽和脂肪酸 」の正体です。
このように常温で個体になる「 飽和脂肪酸 」は、人間の体内でも固まりやすく、摂り過ぎると血液がドロドロになり、動脈硬化など循環器疾患の原因になるのです。
では何故「 飽和脂肪酸 」が人間の体内で固まりやすいのか?
というと、それは動物の血液と人間の血液の温度差が関係しています。
牛と豚の血液の温度は約40℃。鶏で42℃、羊では約44℃。
それに比べて、私達人間の血液の温度は37℃~38℃となっています。
高温の、動物の血液に溶けていた「 飽和脂肪酸 」は、動物よりも低温の、人間の血液内では固まりやすいのです。
日本人は特に「 飽和脂肪酸 」の悪影響を受けやすい体質のため、動物性の脂質を多く含む「 肉 」や「 乳製品 」などの食品は、食べ過ぎに注意が必要だと言われています。
変温動物である魚の脂や、植物の種子から採れる油に含まれる「 不飽和脂肪酸 」は、常温で液体です。
そのため人間の体内でも固まることが無く、血液をサラサラに保ってくれます。
大雑把に言うと「 飽和脂肪酸 」に比べて「 不飽和脂肪酸 」の方が、健康的な油だ・・・と言えるでしょう。
しかし、油には「 絶対に口にしてはいけない危険な油 」が2つあるのですが、それはどちらも「 不飽和脂肪酸 」です。
このため「 飽和脂肪酸 」より「 不飽和脂肪酸 」が健康に良い・・・とは一概には言えないのです。
「 絶対に口にしてはいけない危険な油 」と「 不飽和脂肪酸 」につては次回の記事から徹底解説していきますので、お楽しみに!
日本人が
飽和脂肪酸の
悪影響を受けやすい
理由は?


それは
これから話すよ♪
日本人は「 肉の脂質 」の悪影響を受けやすい
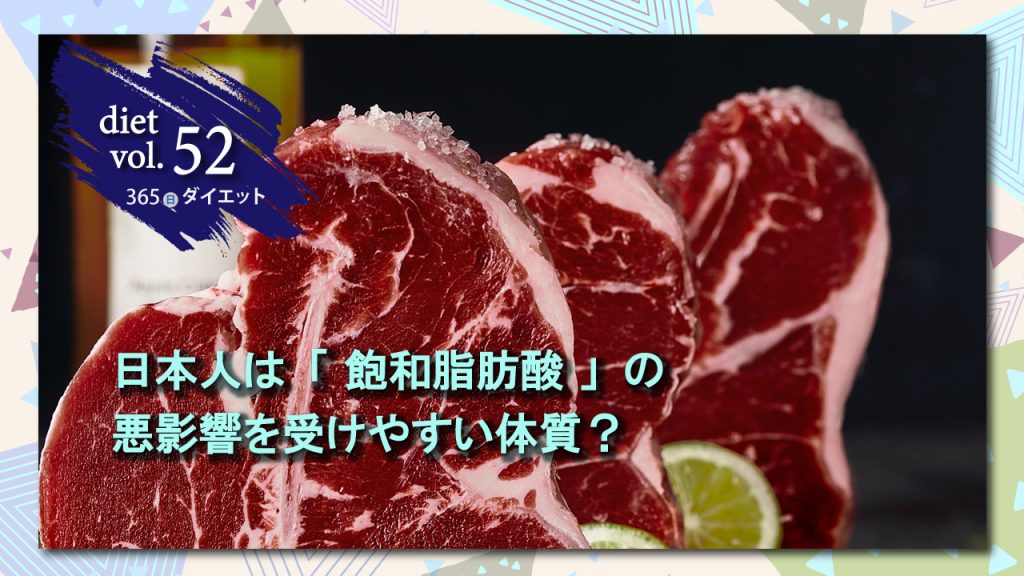
欧米人は「 肉の脂質 」が得意!
ダイエットをするならまず「 基礎代謝 」を上げよう!
というのはダイエットの常套句としてよく聞く言葉です。
これは、以前の記事でも詳しくとりあげましたが真実です。
「 基礎代謝 」と「 ダイエット 」の関係
詳しくはこちらの記事からどうぞ!
【 関連投稿:女性がダイエットに失敗しやすい訳。女性におすすめダイエットとは? 】
基礎代謝とは体温の調節、発汗、消化吸収、内臓の動きなど、無意識で行っている運動のことで、なんと1日の総消費カロリーの約60%を消費しています。
この「 基礎代謝が上がる 」ということは、あなたが意識することなく消費しているカロリーが増える!
ということで、痩せやすくなるのも当然です。
ではどうすれば基礎代謝を上げることが出来るのでしょう?
基礎代謝で最もカロリーを沢山消費しているのは、体熱の産生です。
体熱は細胞内で酸素とエネルギー源( 糖質や脂質 )を反応させて燃焼することで作り出されていて、その体熱を最も多く生み出している細胞が、筋肉細胞なのです。
そのため、筋肉量が多いほど多くのカロリーが消費され、体温も高まる!と言えるのです。
何故、ここでこのような話をしたのかというと、欧米人は日本人と比べて比較的筋肉量が多く、体温が高いという特徴があるのです。
日本人の血液の温度が37℃~38℃なのに対し、欧米人の血液の温度は39℃となっていて、1℃~2℃高くなっています。
このため欧米人は、血液中で固まりやすい飽和脂肪酸の悪影響を、日本人よりも受けにくいのです!
これは元々、欧米人が暮らしていたヨーロッパでは、寒冷な気候のため穀物が育ちにくく、欧米人は栄養を炭水化物ではなく、肉から摂ることが多かったため、脂質を効率よく分解したり、上手く利用できる体質に進化した結果だと言われています。
日本人が「 肉の脂質 」の悪影響を受けやすい理由
日本人は過去、長期間にわたって肉を食べる習慣がなく、主に米( 炭水化物 )や魚から栄養をとっていました。
また、長い歴史の中で、大多数の人間が、その米すらお腹いっぱい食べられない・・・
という低栄養下での生活を強いられてきた背景もあり、日本人の体は低栄養の食事に適応するように進化してきました。
そのため現代の脂質たっぷりの高カロリーな食事に上手く馴染めず、脂質の悪影響を、受けやすくなっているのです。
例えば、日本人の腸の長さは、小腸が約6~8m。大腸が約1.5~2m。
なんとこれは、欧米人より2m近くも長く、低栄養の食事から、余すことなく栄養を吸収できるようになっているのです。
しかし、そのハイスペックな腸のおかげで、日本人のコレステロールの吸収率は欧米人よりも、約20%も高くなっています。
前回みたように、食事から摂取するコレステロールの量で、体内のコレステロール値は、さほど影響を受けない・・・
とはいえ、日本人は欧米人に比べて長い腸のおかげで、食べ物に含まれるコレステロールの影響を受けやすい体質なので注意が必要なのです。
またLDLコレステロールが体内に増えると、自然とHDLコレステロールの合成も増える欧米人に対して、日本人はHDLコレステロールの生成が少なく、LDLコレステロールの値が上がりやすい。ということも分かっています。
これもコレステロールを多く含む食品を、摂取する機会が少なかった日本人にとって、LDLコレステロール値を下げる機能は、それほど重要視されてこなかった。ということでしょう。
LDLコレステロールは肝臓から全身の細胞へコレステロールを届けているが、余ったコレステロールを血管内に放置してしまい、それが動脈硬化を引き起こす。LDLコレステロールが多すぎることが動脈硬化の原因となる。
HDLコレステロールは血管内に放置された、余ったコレステロールを回収し、肝臓へ戻している。
そのためHDLコレステロールが少なすぎることも動脈硬化の原因となる。
また脂質を体内でエネルギーとして燃焼させる際に必要な「 L - カルニチン 」と言う成分も、日本人の保有量は欧米人に比べて少なくなっています。
この「 L - カルニチン 」は、そもそも肉を食することで補充、蓄積できる成分です。
日本人は欧米人に比べて「 L - カルニチン 」の吸収効率が悪く、体内の保有量が少ないというのも、過去に肉をたくさん食べる習慣がなかったからなのです。
このように、日本人は、肉に含まれる脂質の悪影響を受けやすいだけでなく、肉の持っている大切な栄養素を正しく吸収したり、脂質をエネルギーとして利用したり・・・といったことが苦手な体質なのです。
これらのことから、日本人は特に、肉に含まれる脂質( 飽和脂肪酸やコレステロール )の摂取に関しては慎重になる必要がある!
と言えるでしょう。
まさか体温が原因で
飽和脂肪酸が駄目だなんて・・・


さらに女性は筋肉量が少なく
男性に比べて体温が低いから
気を付けないとね。
あ!
「 ハードな取組み 」って
まさか・・・
肉を食べちゃ駄目!
なんて言わないわよね?


あははは!
安心して。
肉は食べるべきさ!
「 肉 」を食べる際の注意点

日本人は特に肉に多く含まれる飽和脂肪酸やコレステロールから悪影響を受けやすい。
ということは、分かっていただけたと思いますが・・・
「 肉食は長寿の秘訣!高齢者こそ肉を食べましょう!! 」
なんてことを言われているのを、耳にしたことがある人も多いはずです。
そもそも肉は食べるべきなのでしょうか?
それとも避けるべきなのでしょうか?
ダイエット中でも「 肉 」は必須で食べるべき?
日本人は肉を食べ過ぎてしまうと、飽和脂肪酸やコレステロールの影響を受けやすい・・・
と言うと、今度は極端に肉を避けたり。
ダイエットと平行して、いきなりヴィーガンを目指そうとする人がいるのですが。
それは正直、おすすめ出来ません。
何故なら・・・
特定の栄養素を極端に排除するような、ダイエットは健康を害する元になることがあるのです。
そもそも、ダイエットなどしていなくとも、現代の食生活は栄養が偏りがちです。
例えば、朝はトーストとコーヒーのみ。
昼はおにぎりを軽くつまんで、夜はカレーや揚げ物・・・
なんて食事を摂っている人も少なく無いはずです。
このように極端に偏った食事を摂っていると、ビタミンや鉄分など、特定の栄養素だけが不足してしまう " 隠れ栄養失調 " といった状態になることがあります。
特に女性は月経や出産で、鉄や亜鉛を大量に失い、さらに育児や仕事で忙しく、自分の食事をおろそかにしがちです。
女性の " 隠れ栄養失調 " は、慢性的な頭痛や激しい月経痛などの原因になることもある!
と言われていて、じつは「 タンパク質 」も、意外と足りていない人が多い栄養素の一つなのです。
皆さんご存じの通り、タンパク質は筋肉の原料です。
タンパク質の摂取量が足りなければ当然、筋肉量が減少します。
タンパクが足りていない食事のうえに、さらに運動を全くしない・・・といった生活習慣を若いときに身に付けてしまうと。
将来、加齢とともに極端に筋力が落ちてしまい日常生活に支障をきたしてしまう、サルコペニアを引き起してしまう原因にも、なりかねません。
「 肉 」は必須アミノ酸( 体内で合成できないため、必ず食事で摂る必要のあるタンパク質の成分 )の全てを含む、優秀な「 タンパク源 」で、健康に生きていくために是非とも食べるべき食品です。
当然ですが、ダイエット中であっても、肉は食べるべき食品なのです。
というよりも健康的に美しく痩せるために、肉は必須で摂るべき食品と言っても良いでしょう。
あなたが今摂っている偏った食事を改善することなく
さらにヴィーガンやベジタリアンを目指せば、当然ますます不健康になってしまいます。
もしあなたが真剣にヴィーガンになりたい。
と考えているのであれば!
偏った栄養バランスの食事を改善し、まずは最高の体調を手に入れ、ダイエットに成功しましょう。
そして適正な体重とそれを維持出来る、食事と運動習慣を、しっかり身に付けてから改めてヴィーガンに挑戦しましょう。
日本人は、肉に含まれる脂質の摂取に気を付けなければいけない。
しかし肉はダイエット中であっても食べるべきだ!
ということが、分かっていただけたと思います。
ここからは、日本人の体質にあった、正しい肉の食べ方にポイントを絞って見ていきましょう。
肉を口にする際に気を付けるべきこと
- 野菜も一緒にしっかり摂る
- 飽和脂肪酸の少ない肉と脂質の少ない部位を選ぶ
- 食べ過ぎない
「 肉 」と一緒に「 野菜 」も、しっかり摂ろう!
脂質をたくさん含む、肉などの動物性タンパク質は、消化に時間がかかるため、消化不良をおこしやすい食品です。
さらに日本人は脂質を乳化して消化しやすくする働きのある胆汁酸の分泌も欧米人に比べると少なく、肉を食べ過ぎると消化不良を起こしやすい体質です。
そして消化不良を起こした未消化の食品は、腸内の悪玉菌の大好物です!
そのため肉を食べ過ぎると、腸内環境が悪化します。
そして、乱れた腸内環境は・・・
これは、前回詳しく見ましたが、もう一度ざっと復習しておきましょう。
良い腸内環境では善玉菌が、食物繊維を餌にして行う発酵活動により、短鎖脂肪酸を作り出し腸内は酸性に保たれています。
この短鎖脂肪酸にはコレステロールの合成を抑える働きがあり、また食物繊維は、コレステロールを吸着して便と一緒に体外へ排出してくれるため、食物繊維を多く含む野菜を食べるとダブルの効果でコレステロール値を下げてくれる効果が期待出来るのです。
一方、荒れた腸内環境では、未消化の食品を餌に、悪玉菌が腐敗活動を行い、アンモニアなどの毒素を出し腸内はアルカリ性に傾くため、酸性の環境を好む善玉菌は弱ってしまいます。
そのため、コレステロールの合成を阻害してくれる短鎖脂肪酸の生成が減り・・・
さらに善玉菌の餌である、食物繊維が腸内に少ないと、腸内に余ったコレステロールが体外に排出されることなく、ばっちり吸収されてしまう!
ということになり、結果LDLコレステロール値が跳ね上がる!という仕組みでした。
コレステロール値を正常に保つためには、肉を食べ過ぎない。さらに野菜をしっかり食べる。
この二つが非常に重要なのです。
「 飽和脂肪酸の少ない肉 」と「 脂質やコレステロールの少ない部位 」を選ぼう!
肉を食べる際にはまず、できるだけ飽和脂肪酸の、少ない肉を選ぶようにしましょう。
飽和脂肪酸の含有量
牛肉 > 豚肉 > 鶏肉
牛肉、豚肉、鳥肉の中では、牛肉が最も多くの飽和脂肪酸を含んでおり、次に豚肉で、次に鶏肉となっています。
できるだけ牛よりも、豚や鶏を選びましょう。
また出来るだけ、脂質やコレステロールの少ない部位を食べるようにしましょう。
ざっと、脂質とコレステロールの部位別含有量をご紹介しておきます。
豚肉の、食べて良い部位と、控えたい部位は下記のようになっています。
| 食べて良い部位 | 脂質( g ) | コレステロール( mg ) |
| 肩 | 7.8 | 55 |
| もも | 7.4 | 60 |
| ヒレ | 4.5 | 60 |
| ロース | 13.2 | 55 |
| 控えたい部位 | 脂質( g ) | コレステロール( mg ) |
| 腎臓 | 5.8 | 290 |
| 肝臓 | 3.4 | 250 |
| 胃腸 | 27.2 | 180 |
豚肉では、もも、ヒレ、肩、などがおすすめです。
内臓系は脂質は少なくとも、コレステロールが多いものが多く、避けたい部位です。
これは牛でも同じです。
次は鶏肉を見ていきましょう。
| 食べて良い部位 | 脂質( g ) | コレステロール( mg ) |
| ささみ | 0.5 | 55 |
| 胸 | 2.4 | 70 |
| もも | 7.4 | 90 |
| 控えたい部位 | 脂質( g ) | コレステロール( mg ) |
| 肝臓 | 3.1 | 370 |
| 腸 | 18.9 | 210 |
| 皮 | 45.3 | 120 |
鶏肉は、ささみ、胸、ももなどが、脂質やコレステロールが少なくおすすめです。
やはりレバーや内臓系はコレステロール値が高く、鶏は皮に脂質が多いので注意が必要です。
肉を食べるときは出来るだけ、牛を避け、豚や鶏を選ぶ。
そして内臓系を避け、高タンパク低脂肪な赤身肉。
鶏肉であれば、ささみ、胸、もも等を選ぶと良いでしょう。
「 肉 」は普段から食べ過ぎない
若いうちは、多少、脂質やコレステロールの多い肉を多少食べ過ぎても、肉と一緒に野菜もしっかり摂ることで、腸内環境の悪化を防ぐことができますし、消化酵素の分泌も盛んなので、消化不良を起こすことは無いかも知れません。
しかし、加齢と共に徐々に消化酵素の分泌量はだんだんと減っていきます。
消化液( 酸性 )の分泌量が減ると、腸内環境はアルカリ性に傾きやすくなります。
また消化酵素が減ることで、消化力が弱り、未消化の食べ物が大腸内に運び込まれる機会が増えます。
このため、高齢になるほど、腸内は、悪玉菌にとって有利な環境になりやすく、コレステロール値が上がりやすいのです。
では高齢者は「 肉 」を食べない方が良いのか?
というと、そうではありません。
高齢者こそ、筋肉量と筋力を維持する為に、肉を食べることが推奨されています。
しかし元々脂質の消化・吸収が苦手な日本人は、消化力が弱ることで、加齢とともに「 肉 」が食べられなくなる人が多いのも特徴です。
そのため日本人は、もともと少ない筋肉が加齢と共にさらに減り、日常生活に支障をきたすほど筋力を低下させてしまう、サルコペニアを発症するリスクが高いのです。
自分はまだ若く、暴飲暴食しても平気だからと、あまりにも消化器官に負担をかけ過ぎていると・・・
年をとってから「 肉 」を食べるべきときに「 肉 」が食べられない・・・なんてことになるかも知れません。
年をとってもなお!肉をしっかり食べられる消化力を保てるように、若い時から、消化器官に負担をかける暴飲暴食はできるだけ避けましょう。
日本人は、しっかりとした知識を持って、正しく「 肉 」を食べることが求められているのです。
肉は、食べ過ぎに注意するとともに、野菜も、しっかり食べる!
そして腸内環境を常に良好に保つ!ということが、老若男女問わず非常に重要なことなのです。
肉を食べ過ぎない・・・
って一体どれくらい
食べてもいいのかしら?


肉は一食
100gが目安だね。
100gって・・・
ステーキ100gで
頼む人・・・いる??

「 肉 」の適量は?
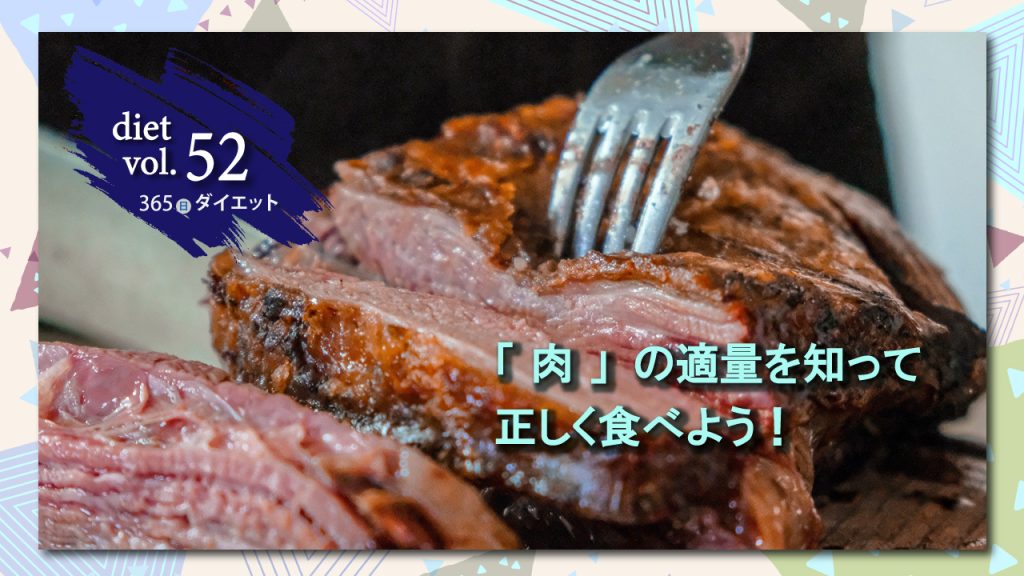
肉は摂り過ぎに注意しつつ、しっかり摂りましょう。
とはいえ、一体どのくらいの量を食べるのがベストなのでしょうか?
お肉の最適な摂取量について、詳しく見ていきましょう。
一日に必要な「 タンパク質量 」を把握しておこう
一般的な成人男女の、一日におけるタンパク質の推奨摂取量は、体重1キログラムあたり0.8グラムとされています。
もちろん生活スタイルや、運動の習慣の有無で、必要なタンパク質の量は変わります。
たとえば、ハードな筋トレをしている人は、体重1キログラムに対して、1.5グラム~2グラムのタンパク質が必要とも言われています。
体重55キロの私は、通常であれば44グラム。
しかし私はハードな筋トレを行っているので、80グラム~110グラム程度のタンパク質が必要。
という計算になります。
私は男性にしては小柄な方なので、これは女性の平均的な摂取量と思っても良いかもしれません。
実際、厚生労働省発表の、一日のタンパク質の推奨摂取量は、成人男性で65g、成人女性は50gとなっています。
大まかには、一食に20グラム( 高齢者では20~30gとなっています )を目安に摂ると良いとされていて、男女とも、おおよそこの数値を摂取量の目安にすれば良いでしょう。
「 肉 」はどのくらい食べれば良いの?
いったいどのくらいの肉を食べれば、タンパク質20gが摂れるのでしょう?
まず、肉に含まれるタンパク質量を見ていきましょう。
鶏胸肉、牛肉( 赤身 )ともに約85~100グラム中に、約20~25グラムのタンパク質を含んでいます。
お肉に含まれるタンパク質は大体、100グラムで、おおよそ20グラム程度と思って良いでしょう。
ということは、一食の目安はお肉であれば、100gということになります。
ステーキを食べる時、150~200グラム程度を注文するのが一般的だと思いますが・・・
200グラムだと、タンパク質40g。これは運動習慣がある人の摂取量です。
300グラムになると、タンパク質60グラム。これは摂り過ぎで、腸内環境の悪化が懸念されます。
あなたが今、とくにハードな運動の習慣がないのであれば・・・
肉は一日に一回、100グラム。
多くても150グラム程度に抑えて、後の2回の食事は、飽和脂肪酸やコレステロールの摂り過ぎを抑えるために、肉以外のタンパク源から、一食20g以上のタンパク質の摂取を目指すのが理想です。
「 肉 」以外の「 タンパク源 」も組み合わせて摂ろう
肉以外の食品が含むタンパク質量も見ておきましょう。
魚だとサーモン、マグロなどで、85~100グラムに、20~25グラムのタンパク質を含んでいます。
魚も肉とほぼ同じで、100グラムで大体20グラム程度のタンパク質を含む。
と考えておいて差し支えないでしょう。
ちなみにシャケの切り身一切れが、大体80g程度と考えると、魚は一食分で大体20グラムを、ほぼまかなえていると考えて良さそうです。
これら肉や魚をメインに、その他タンパク質を含む乳製品や卵、植物性のタンパク質を豊富に含む、大豆製品などを組み合わせて、一食20g以上のタンパク質摂取を心がけましょう。
参考までに、タンパク質の含有量の多い食品に含まれる、タンパク質量をまとめておきますね!
| 食品 | 一食分の分量 | タンパク質( g ) |
| 肉類 | 100g程度 | 約20g |
| 魚介類 | 100g程度 | 約20g |
| 豆腐 | 1/3丁( 約100g ) | 6~7g |
| 牛乳 | コップ1杯( 約200ml ) | 6~7g |
| 豆乳 | コップ1杯( 約200ml ) | 6~7g |
| 卵 | 1個( 約50g ) | 約7g |
| 納豆 | 1パック( 約50g ) | 約8g |
| ヨーグルト | 100g程度 | 約4g |
| プロセスチーズ | 1個( 約18g ) | 約4g |
例えばですが
朝は卵と納豆、味噌汁、ヨーグルトで、約20g
お昼は、焼き魚定食で、約20g
夜はお肉100gで、約20g
などなど・・・工夫して、肉、魚、乳製品、大豆などから、バランス良くタンパク質を摂ることで「 飽和脂肪酸 」や「 コレステロール 」の摂り過ぎを防ぎつつ、しっかりとタンパク質を摂りましょう。
タンパク質の摂り過ぎは
腎臓に負担をかけるから
良くないって聞いたことあるけど?


腎臓に負担をかける程
タンパク質を
食事で摂ろうと思っても
気持ち悪くなって・・・
食べられないと思うよ。
そうなのね!


ただプロテインを一日
何回も飲んだり
して過剰摂取していれば・・・
悪影響が出るかもね。
じゃあ今日の取組みを
発表するよ♪
今回の取り組み
- 肉は出来るだけ牛肉を避け、鶏肉か豚肉を選ぼう!!
- できるだけ脂質やコレステロール値の低い部位を選ぼう
- 肉は一食100グラム程度に抑えて、野菜をしっかり食べよう!!
- タンパク質は、肉、魚、乳製品、大豆などからバランス良く、一食20グラムを目安に摂ろう!!
肉は出来るだけ鶏肉か豚肉にして
結論、食べ過ぎないって・・・
特にハードな取組みでもなかったわね。


今回はね!!
でも覚悟だけはしておいてよ。
ちゃんとハードになってくるから。
今回のまとめ
肉に主に含まれる脂質「 飽和脂肪酸 」は
高い体温の動物の血液内では、液体で存在していますが
動物よりも体温の低い人間の血液内では固まりやすく、血液をドロドロにしたり
動脈硬化の原因となってしまいます。
特に日本人は、欧米人と比べて
体温が低い傾向にあるため
飽和脂肪酸の「 血液内で固まりやすい!」
という悪影響を受けやすいのです。
さらに、過去長い期間、肉を食べる習慣を持たず
主に穀物( 糖質 )から栄養を摂ってきた日本人は
欧米人に比べて、脂質の悪影響を受けやすいだけでなく
脂質をエネルギーとして利用することも苦手な体質なのです。
これらのことから
日本人は欧米人と比べて
肉を食べたときの良い面は享受できず
肉に含まれる脂質の悪影響を受けやすい体質!
と言えるでしょう。
しかし肉は非常に優秀なタンパク源で、是非摂るべき食品です。
飽和脂肪酸の悪影響を減らすために
牛肉よりも、飽和脂肪酸の少ない、鶏肉、豚肉を選んで食べる。
コレステロールの悪影響を軽減するため
コレステロールの少ない部位を選んで食べる。
また腸内環境を悪化させないために
食べ過ぎに注意して野菜もしっかり食べる。
といったことに注意して
ダイエット中であっても
適量の肉を食べましょう。
といった内容でした。
次回は
絶対に口にしてはいけない!!
危険なあぶら「 トランス脂肪酸 」について
くわしく見ていきますよ!!
お楽しみに♪



